| |
|
| 「京扇子」「京うちわ」は京都扇子団扇商工協同組合の登録商標(地域団体商標)です。 当組合員以外は使用できません 。 |
|
桧 扇
|
 |
檜扇とは檜の薄片を末広がりに綴り合わせ、手もとに要をつけ、先を絹の撚糸で編み綴った板扇であり、表に金銀箔を散らし、彩絵して束帯など、平安宮中の公の儀式の際の持ち物でした。木簡から派生したと考えられ、東寺の千手観音像の腕の中から発見された元慶元年と記された物が、我が国最古の檜扇とされている。当初は男性が用い、女性は「はしば」という団扇の一種を持っていましたが、次第に女性も檜扇を用い初め、宮中の女人が常に手にするようになりました。初めから装飾的役割が与えられていたが、特に女性が用いるようになってさらに彩り華やかな物になりました。国風文化が花開く中に優雅さと繊細さを加え、平安時代中期には、三重、五重(みえ、いつえ)と呼ばれる数多い矯数(骨数)の扇ができ、草花、人物などが彩られ、美しい彩糸を長く垂らしていました。 | |||
|
蝙幅扇
|
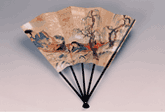 |
檜扇に次いで平安時代から作られ始めた紙扇で、竹を骨とし、片面に地紙(扇面用紙)を貼ったいわゆる片貼扇で、最初は骨の数も5本ぐらいであったが、長保年間(999〜1003年)以前には、金銀泥箔に彩画・詩歌がしたためられ色紙の粋を尽くし、骨数も次第に増えた。その華やかさは、女子用檜扇にも劣らない物であり、男女間の文替わりの扇交換や宮中で侍臣に扇を賜る年中行事「扇の拝」の記録も平安初期に見られます。 | |||
|
絹 扇
|
 |
日本国内で発展した扇子が13世紀頃中国へ輸出され、シルクロードを渡りインドを経て遠くヨーロッパまで伝わりました。ルイ王朝社交界で扇子はヨーロッパ風にアレンジされ、象牙やべっこうを骨とし絹やレースを貼った洋扇子が独自に発展します。その後それは日本へ逆輸入され、ここからまた絹や綿布を貼った和風の絹扇が生み出されたのです。 | |||
|
白檀扇
|
 |
香木・白檀の木片を重ねた板扇で、透かし彫りや描き絵の装飾を施します。招涼に用いるというより上品な香りを楽しむ持扇となっています。 | |||
|
能扇
|
 |
室町時代になると武家文化が勃興を迎え、また町人階級の台頭により扇は美術工芸品として、猿楽・能楽などの芸能に用いられるようになって発達した紙扇。扇骨、図柄とも流派による伝統的な約束事がおおく、華やかな雰囲気を持つ扇です。 | |||
|
舞扇
|
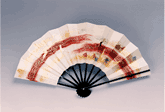 |
能扇同様に室町時代以降に発展した舞踏用の紙扇で芸術的工芸品の域に達し、飾り扇としても世界的にも有名である。 雲や霞、水などの図柄が多く、その使われ方から、竹骨に鉛を埋め込むなど、扇の造りに一定のスタイルがあります。 | |||
|
茶席扇
|
 |
能扇同様に室町時代以降、茶道の発展とともに発展し、茶席に用いられる紙扇。一般では婦人用五寸、紳士用六寸の長さのものが多く使われています。 | |||
|
祝儀扇
|
 |
冠婚葬祭用の扇子で、縁起物だけに昔からの約束事があり、男女によって地紙や扇骨に特徴があります。また、最近は洋装の儀式のものもできています。 | |||
|
有職扇
|
 |
宮中や神社、仏閣で用いられる扇子です。現在でも古来からの礼式・故事に従って製造され、今ではもっとも特殊な製品となっています。 | |||
